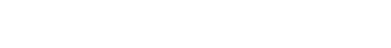現在、多くの国内スポーツチームがアジア市場へ進出する中、先進的な取り組みを行うのがJリーグの浦和レッズと、その責任企業である三菱重工だ。サッカー熱の高いタイでの活動について、アジアのスポーツビジネスに詳しく、スポーツ庁の国際展開支援プラットフォーム「JSPIN」アドバイザーも務める小山恵氏が解説する(文=FAR&EAST小山恵氏)(初出=JSPIN)
東南アジアで進む二人三脚の挑戦
近年、日本のスポーツチームがアジア市場での存在感を高める動きが加速している。国際的な競争が激しさを増す中、スポーツと産業が手を取り合い、海外での活動を通じて互いの価値を高める事例はまだ多くない。その先進的な取り組みが、浦和レッズと責任企業である三菱重工によるアジア戦略だ。
浦和レッズは、AFCチャンピオンズリーグで3度の優勝を果たすなど、アジア屈指のビッグクラブとして広く知られている。特にサッカー熱の高いタイでは、ACLでの戦いぶりや日本代表選手の所属歴もあり、クラブの知名度とブランド力は群を抜く。現地では、多くの少年少女が「将来は浦和レッズでプレーしたい」と夢を語るという。
一方、三菱重工はタイ国内に7,000人を超える従業員を抱え、空調機器や産業機械、インフラ事業など幅広い分野で長年現地社会に貢献してきた。強固な事業基盤を持つ一方で、社員の一体感やブランドの親しみやすさといった“ソフト面”の価値向上は、今後、取り組むべき事項として捉えていた。
強豪クラブとの提携が生んだ新たな舞台
両者の連携が本格化したのは、タイの強豪ムアントン・ユナイテッドとの提携がきっかけだった。浦和レッズは同クラブとパートナーシップを締結し、選手交流や指導者交流、育成年代の支援を展開。三菱重工もムアントンのスポンサーとして加わり、地域社会と社員を巻き込んだ多層的なプロジェクトが動き出した。
この連携の象徴が、「Mitsubishi Heavy Industries Diamond Cup U-14 Thailand」だ。タイ国内での開催は今年で4回目を数え、今年はシンガポールやオーストラリアなど国外からも参加チームが集まる。毎年浦和レッズのU-14チームも参戦し、レベルの高い熱戦が繰り広げられる。日本とは違い、育成年代の大会・環境が整備されていないタイにおいて、このようなレベルの高い国際大会は貴重であり、参加する子どもたちにとっては夢のような時間となっている。
さらに、この大会の優秀選手は毎年日本に招待され、浦和レッズアカデミーの練習に参加している。これは彼らにとって大きな憧れであり、サッカー技術だけでなく、異文化交流や国際的な視野を広げる貴重な経験となっている。継続開催によって、大会を経験した選手が将来プロや代表選手になる可能性も十分にある。実際、過去の参加者の中には年代別代表に選ばれた選手もおり、この大会は“夢への登竜門”としても注目を集めている。
「タイにおいてこの大会を開催することや、プロサッカークラブのパートナーとなることは、当初考えていたよりも様々な面で社員のエンゲージメント向上につながっています。その取り組みが、自社で働くことの誇りやモチベーションにつながるように今後も新たな施策を打っていきたいと思います。
また、この成功事例を東南アジア他国でも水平展開したいと考えています。それは、この活動がタイの子どもたちに夢を与えていることを実感し、大会の回数を重ねるごとに私たちのモチベーションにもつながっているからです」 (三菱重工 広報部 渡辺氏)
三菱重工にとって、この大会は単なる広報活動ではない。毎年、現地社員の家族を対象にしたサッカークリニックを開催し、子どもたちが浦和レッズのコーチから直接指導を受けられる機会を提供している。このイベントは社員から非常に好評で、家族ぐるみで企業活動に誇りを持つきっかけとなっている。
さらに、大会期間中には浦和レッズU-14の選手たちが三菱重工の現地製造拠点を訪問し、ローカルスタッフと親善試合を行う恒例イベントもある。サッカー熱の高いタイならではの盛り上がりを見せ、社員同士の交流や一体感の醸成に大きく貢献している。こうした取り組みが、社員満足度やエンゲージメント向上に直結しているのだ。
クラブと企業が共に築く現地との関係
浦和レッズにとっても、この連携は海外戦略の大きな推進力だ。現地に拠点や社会的信頼を持つ企業と協働することで、単独では到達しづらい地域や層に深く入り込むことができる。
「アジアでの活動は、単発のイベントではなく“継続”することにこそ意味があると考えています。4年前にこの大会に参加した14歳の選手たちは、今や18歳となり、プロとして羽ばたく年代に差し掛かっています。その時に、浦和レッズや三菱重工と共に過ごした経験を思い出してもらえれば何よりです。
特にMVP選手として日本に来て、浦和レッズのトレーニングに参加したことが、良き思い出や自信につながってほしいと願っています。アジア全体を見渡すと、資金や力が中東に集中していますが、私たちは東アジアの育成や競技レベルを底上げすることで、欧州クラブにも肩を並べられる存在を目指したいと考えています」(浦和レッズ 成長推進室 矢島氏)
このアプローチにより、クラブは現地のサッカー文化や社会に根を張り、企業は自らの事業活動と連動した持続可能なブランド価値を構築できる。

筆者の考察:欧州クラブとのアプローチの違い
欧州のビッグクラブがアジアで展開する戦略は、多くの場合「既に存在するアジア市場からいかに収益を得るか」に軸足がある。スター選手の招聘、短期ツアー、グッズ販売など、ブランド力を前提とした「収益回収型」モデルだ。例えば、タイにおける英プレミアリーグの放映権料は年間100億円を超えると言われており、その収益規模は単一国としては世界でも有数であり、欧州リーグやクラブにとって魅力的な市場となっている。
一方、浦和レッズと三菱重工の取り組みは、市場そのものを育て、拡大させていく「市場共創型」モデルである。クラブと企業が地域と一緒に成長し、現地の人々の夢を支えるストーリーを紡ぐ。タイの子どもたちが「いつか浦和レッズでプレーしたい」と夢を見る。その夢を叶えるための舞台を、クラブと企業が共に整えていく姿は、欧州クラブには容易に真似できない。
日系企業が持つ長期的な現地密着経営と、クラブの地域志向的な価値観が組み合わさることで、双方にとって持続性のある成果が生まれる。この関係性は、単なるスポンサーシップの枠を超え、スポーツが企業の経営資源の一つとして機能する未来像を描いている。
浦和レッズと三菱重工の取り組みは、決して特殊なケースではない。
Jリーグのクラブにおける責任企業の多くは、グローバルに事業展開する大企業であり、アジア・東南アジアはその中でも極めて重要な市場だ。現地でサッカー人気が高いという土壌を生かし、クラブと親会社が協業して活動すれば、企業にとっては社員や地域社会との接点を強化でき、クラブにとってはファン基盤を拡大できる。両者にとって大きなシナジーと価値が生まれる構造である。
こうしたモデルはサッカーだけに限らない。他の競技でも同様の展開が十分に考えられる。たとえば、バレーボールのSVリーグに所属する大阪ブルテオンは、親会社のパナソニックと連携し、タイでの興行試合を開催している。バレーボールが盛んな東南アジアで親会社と共に現地に根差した活動を行うことは、まさにレッズと三菱重工のアプローチと同じ文脈に位置付けられる。
今後、日本のスポーツと日本企業が一体となり、アジア各国での交流・事業展開を推し進めていくことは、サッカーに限らず、日本のスポーツビジネス全体に新しい地平を拓く可能性を秘めている。
広がる可能性と未来
浦和レッズと三菱重工の取り組みは、現地のサッカー少年だけでなく、従業員や地域住民、自治体、教育機関など、多様なステークホルダーを巻き込むことができる。結果として、企業にとってはブランド価値や社員ロイヤリティの向上、クラブにとってはファン基盤の拡大、地域にとってはスポーツ文化の発展という“三方良し”の成果が期待できる。
浦和レッズと三菱重工は、今後ベトナムやインドネシアなどASEAN全域への展開も視野に入れている。アジアの若者たちにとって浦和レッズは憧れの象徴であり、その舞台を支える三菱重工は夢の伴走者だ。この「共に成長する」アプローチこそが、日本型スポーツビジネスの新しいスタンダードとなる可能性を秘めている。
◇小山 恵(こやま・けい)
株式会社FAR&EAST 代表取締役
2012年Jリーグのアジア戦略・海外事業の立ち上げから主要メンバーとして参画。アジア戦略黎明期からJリーグの東南アジアでの市場開拓をリード。2022年に株式会社FAR&EASTを創業、スポーツ団体・企業等の海外・アジアでの事業展開をサポート。JSPINアドバイザー(専門エリア:ASEAN)
JSPINでは他にも海外展開の事例を紹介しています。以下のバナー〈こちら〉から。