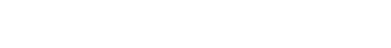スタジアムが「体験装置」として捉えられるようになった現在、欧州サッカー界では様々な体験施策を各クラブが生み出しています。そうした施策について、全体像を捉え、分類し、今後の設計に活かそうと提供されているのが、SPSGコンサルティング社による「顧客体験の9つの分類軸」です。
顧客体験をどう設計していけばよいのか? そして、欧州における先行事例とは? 今年9月開催の「World Football Summit(WFS)香港」にあわせ、WFS日本市場代表の堀口創平氏が解説する第3回です。(文=WFS堀口創平氏)(全4回の3回目/第1回を読む)
顧客体験の「9つの分類軸」
スポーツ専門コンサルティングファームのSPSGコンサルティングでは、「顧客体験」を9つの分類軸で構造化するフレームワークを提唱しています。
- 体験の性質:衛生的(Hygienic)/付加価値型(Enhancing)
- 提供チャネル:現地型(Onsite)/オンライン型(Online)
- 実施タイミング:試合日(Match Day)/非試合日(Non-Match Day)
- カスタマイズ性:標準型(Standard)/個別最適化型(Personalized)
- ターゲット:B2B向け/B2C向け
- 実施主体:自社所有(Own)/第三者提供(3rd Party)
- パッケージ性:単体型(Isolated)/パッケージ型(Packaged)
- 参加性:受動的(Passive)/能動的・参加型(Interactive)
- 継続性:単発型(One-off)/季節型(Seasonal)
9つの分類に対して、体験を対比構造(AかBか)で捉えているのが特徴ですが、重要なのはどちらか一方が「正解」ではないということ。クラブの文化やファン層に応じて、どの軸をどう設計するかが体験戦略の個性になります。

9分類軸を解説する前編となる本稿では、1〜5を詳しくみていきましょう。
1. 体験の性質:衛生的(Hygienic)/付加価値型(Enhancing)
まず、どれだけ優れた演出や技術が導入されていても、「入場がスムーズでない」「座席が汚れている」「トイレが混雑している」といった基本的な部分が欠けていれば、ファンの全体的な満足度は大きく損なわれます。こうしたHygienic(衛生的)な体験は、スポーツ観戦に限らず、あらゆる空間体験における土台であり、目立たないものの重要な要素です。
実際、スポーツ界ではしばしば「体験価値=演出やテクノロジー」と捉えられがちですが、土台が不安定なままでは付加価値(Enhancing)も活きません。たとえば、音響が素晴らしくても「ピッチの半分が見えない」「スマホがつながらない」という状況では、感動は生まれにくいのです。
例えば、2024年パリ五輪において、清掃・警備・空港サービスなどを担ったOnet社(フランス)のように、裏方で快適さを支える存在は、決して過小評価すべきではありません。快適な導線、清潔な施設、ストレスのない入退場こそが、すべての体験の出発点なのです。
2. 提供チャネル:現地型(Onsite)/オンライン型(Online)
体験の「場所」は大きく2つに分かれます。スタジアムなど物理的な空間で行われる現地型(Onsite)と、SNSやライブ配信、アプリなどを通じて提供されるオンライン型(Online)です。近年ではこの2つが組み合わされ、体験がハイブリッド化するケースも増えてきました。
現地型体験の設計に長けた企業として知られているのがLegends社(アメリカ)で、FCバルセロナ(スペイン)やマンチェスター・シティ(イングランド)など欧州トップクラブのホスピタリティエリアや展示空間の設計を数多く手がけています。施設設計から動線設計、収益最大化の導線までも含めた空間体験の総合プロデュースが特徴です。
一方、DAZNが展開する視聴者投票機能やSNS連動企画などは、デジタル上でファンが試合に対して能動的に関与する仕組みとして注目されています。リアルとバーチャルの接点を設計することで、ファンの没入感や愛着は大きく高まります。
また、カンクンFC(メキシコ)では、VIP観戦エリアにジャグジーを設けるなど、リゾート地ならではの非日常を意識したユニークな現地体験が話題を呼んでいます。物理空間を活かした遊び心のある設計が、強烈な記憶を生み出す好例です。

3. 実施タイミング:試合日(Match Day)/非試合日(Non-Match Day)
かつて、スタジアムは「試合がある日だけ」の場所と捉えられていましたが、今やその発想は過去のものとなりつつあります。近年では、非試合日(Non-Match Day)にも価値ある体験を創出することで、施設の稼働率とファン接点の最大化を目指す動きが加速しています。つまり、スタジアムは“365日稼働する体験装置”へと進化しているのです。
たとえば、スペインのスタートアップ企業であるBStadium社は、スタジアムツアーに観光要素を掛け合わせることで、非試合日の来場体験をアップグレードしています。具体的にはスタジアム内のフォトスポット巡りや、ARを活用したスタンプラリー型アクティビティ、クラブストアや飲食との連動企画などを通じて観光客やライト層を取り込むことに成功しています。
このような施策により、収益機会の多様化だけでなく、クラブのブランド接触機会も大きく増加。試合がない日でもスタジアムを訪れる理由がある、という状態をいかに作れるかが、これからのベニュー戦略の分岐点となります。
4. カスタマイズ性:標準型(Standard)/個別最適化型(Personalized)
近年のトレンドは、「誰にとっても同じサービスを提供する」画一的な標準型(Standard)から、一人ひとりに寄り添う体験を追求する個別最適化型(Personalized)へのシフトです。テクノロジーの進化とともに、年齢、言語、身体的特性、嗜好などに応じて、個々のニーズに合わせた体験設計が可能になりつつあります。
こうしたパーソナライズド体験は、単なる満足度向上にとどまらず、アクセシビリティ(利便性)やインクルーシビティ(包摂性)の向上にもつながる重要な要素です。つまり、すべての人に開かれたスタジアムづくりの基盤にもなるのです。
例えば、RCデポルティボ(スペイン)は、視覚に障がいのあるファンに向けてスマートフォンアプリを通じてリアルタイムの音声実況を提供しています。この仕組みにより、スタジアム現地にいる人も、自宅や移動中の人も、臨場感ある試合展開を耳で体験できます。これはインクルーシブであると同時に、高度に洗練されたテクノロジー活用の好例と言えるでしょう。
5. ターゲット: B2B向け/B2C向け
体験のターゲットによって、求められる内容や演出の方向性は大きく異なります。企業関係者やパートナー候補などを対象としたB2B向けの体験では、「非日常性」「特別感」「ネットワーキング機会」などが重視される一方、一般ファンを対象としたB2C向けの体験では、「親しみ」「共感」「参加型の要素」などが求められます。
たとえば、カディスCF(スペイン)は、クルーズ船やヨットを活用したネットワーキングイベントを開催し、海沿いの立地を活かした「場所そのものが体験」となるB2B戦略を展開しています。単なる商談の場ではなく、ブランドの世界観を感じてもらう空間としても活用されており、顧客やパートナーとの関係深化を目的としています。
一方、レアル・ベティス(スペイン)では、地域住民やサポーターによるボランティア活動を、体験価値の一部として位置づけています。イベント運営や地域清掃などへの参加が、「B2C向けのファン体験」そのものとして機能しており、ファンがクラブの一員として誇りと帰属意識を得られるような仕組みが整っています。
このように、同じサッカークラブであってもターゲットによって体験設計はまったく異なる方向性をとっており、明確なセグメンテーションと体験設計が、ファンベースとパートナー基盤の両立において鍵となります。
※
いかがだったでしょうか? 連載の最終回となる次回は、この「顧客体験 9つの分類軸」の残り4つを詳しく解説します。
「World Football Summit」が9月に香港で初開催!
2025年9月3日(水)〜4日(木)、香港で、東アジアで初となる「World Football Summit」が開催。スポンサーシップ、メディア、テクノロジー、ファンエンゲージメント、投資などをテーマに世界のサッカービジネスをリードするキーパーソンが集結。海外サッカークラブと新たなビジネスチャンスを見つけたい方、グローバルトレンドをいち早くキャッチしたい方には見逃せないイベントです。https://worldfootballsummit.com/hong-kong/