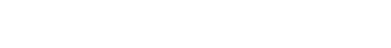トップアスリートの低年齢化、そして現役キャリアの長期化は多くのスポーツで見られる。キャリアが長くなるほどケガと付き合い、そのケアを行う期間も長くなるだろう。
アスリートのキャリアにおいて選手とその周囲はどう連携すればよいのか?テニスプレーヤーの伊達公子氏、NBAロサンゼルスレイカーズ チームドクターのクリストファー・ジョーンズ氏らが、先月都内で開催された「Sports Doctors Network Conference 2025」で語り合った。(全7回の4回目/第1回から読む)
「低年齢化」「長期化」 顕著なテニス界
伊達公子氏といえば日本を代表するテニスプレーヤー。WTAツアー通算でシングルス8勝を挙げ、日本人女子史上初めてシングルス世界ランキングトップ10入りしたレジェンドだ。
高校卒業後の1989年にプロ転向し、95年には世界ランキング自己最高の4位を記録。翌96年に一度引退するも、2008年に現役復帰して17年まで競技の第一線で活躍した。
長くキャリアを築いてきた伊達氏に、モデレーターの村上由美子氏(MPower Partners)が最初に投げかけたのが“選手の低年齢化”だ。「いろんな競技で活躍する選手の年齢がどんどん若くなっているような気がするのですが、いかがでしょうか?」と、村上氏。
「確かに低年齢化してきています。(世界ランキング)トップ10に入っているミラ・アンドレーワは18歳、ココ・ガウフは21歳です。かつてはモニカ・セレスが16歳くらいから、マルチナ・ヒンギスは14歳くらいから活躍していましたね。一時期止まっていましたが、今また低年齢化してきているのではないでしょうか」(伊達氏)

こうした中、選手の低年齢化とともに、現役期間が長くなっている点も指摘する。
「10代の選手がいる一方、30代の選手も多く残っているので、キャリアが長くなっているということがいえると思います。私は90年代にファーストキャリアを戦っていましたが、その頃は選手のキャリアは10年程度と言われていました。出産を経て復帰するというのも、昔はあまりみられなかったことです」(伊達氏)
キャリアが長期化すれば、必然的にケガのリスクも高まる。そもそもテニス界では、世界を舞台に戦う選手は、各地の大会開への移動を続けながらシーズンを送っている。
「月曜に大会が始まって日曜に決勝というサイクルがくり返されるのですが、トップの選手ほど週末まで残る可能性が高くなるので試合数が多くなります。逆にランキングが低い選手は途中で負けてしまって獲得ポイントが少なくなるので、ランキングを上げたいと思ったら大会に参加する回数を増やさなければなりません。
選手にかかるストレスは多いので、睡眠、栄養補給などのバランスは必要不可欠。疲労の蓄積やケガを排除することは難しいので、いかにして壊れない体を作っていくかが求められています」(伊達氏)
特定の競技に集中しすぎることは将来に影響を及ぼす
同じく登壇したクリストファー・ジョーンズ氏は、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)で整形外科医として働きながら、NBAロサンゼルス・レイカーズのチームドクターも10年ほど務める、現役の医師だ。

同氏は若い頃から特定の競技に集中しすぎることによる弊害を指摘する。
「幼い頃から特定の競技に打ち込めば、スキルを習得して競争相手に勝って成功を収められるかもしれません。ただし、ずっと後になってから体への影響が表れる可能性があります」(ジョーンズ氏)
わかりやすい例が、トミー・ジョン手術だ。ひじの内側側副靭帯の再建手術のことで、野球選手、特にピッチャーが投球動作をくり返し行うことよって靭帯を損傷させ、それを修復するために行われる手術がある。
「大谷翔平選手は、すでに2回のトミー・ジョン手術を受けていますよね。特定の部位に同じストレスがかかり続けると衰弱が始まります。負荷が大きすぎると、身体が耐えられなくなるのです。ですから、私たちは若いアスリートたちの指導に、より一層力を入れ始めているのです」(ジョーンズ氏)
同氏は、もっと“休むこと”の大切さをアスリートに理解してほしいとも述べる。
「若い頃は、若さに頼りすぎてしまうところがあります。若さを味方にしてマウンドから投げるのは簡単ですが、休息と回復は重要です。そして、全体的な体の動きに重点をおき、特定の部位に過度の負担がかかってケガをしないように気をつけなければなりません。
私たちは、こうした若いアスリートの負担を軽減するために、真剣にメッセージを出し始めました。7〜8歳で特定のスポーツに特化するのではなく、複数のスポーツを経験し、バランスや柔軟性、そして幼い頃から適切な筋力で体をコントロールする方法を学ぶことが大切だからです」(ジョーンズ氏)
ジュニアアスリートへの大人のサポートが欠かせない

こうしたアスリートに対して、周囲のサポートが欠かせないと両名は話す。
「ケガについて話す際に注意する点は、治療を続けることで試合に出られなくなることをアスリートが恐れてしまうこと。症状の悪化を防ぐことができるにもかかわらず、医師のところにすぐに相談に来ない傾向があります。これが何よりも問題です。
医師として最も重要なのは、ケガの内容を明確に伝えることです。選手が納得できる明確な診断を下し、最高レベルの治療を行うのはもちろん、リハビリ、ストレングス&コンディショニングなどのケアについても選手が信頼するスタッフを迎え入れることも大切です」(ジョーンズ氏)
「確かに私も、とにかく試合をしたい、戦い続けたいという思いで、捻挫や肉離れをごまかしながら試合に出ていたことがありました。きちんととケガの状態を説明してくれる医師、そしてそれに対してどう向き合うかを一緒に考えてくれるチームを持つべきですね。長いビジョンを示して、プロセスを踏んで復帰できることを説明をしてくれる人たちがいないと、選手は、『試合をしたい』『負けたくない』と考えてしまいますから」(伊達氏)
現在はジュニア選手への指導にもあたる伊達氏。選手を正しく導く大人の役割にも言及する。
「彼女たちは痛みを感じても、ドクターに診てもらおうという意識が低いと感じます。選手自身にも、そして指導者やコーチにも、“ケアをすることは強くなるためのプロセス”だということを理解してもらいたいですね。
私自身もそうでしたが、若い頃は『寝れば治る』と思いがちなんです。自分の体の状態をうまく言語化できないジュニア世代の発するシグナルを、指導する周りの大人が汲み取ってあげることが必要です」(伊達氏)
ジョーンズ氏は最後に、医師としてジュニア選手を取り巻く大人たちにメッセージを残した。
「ケアチームのみなさんは、アスリート自身に、すべてを一人ではできないのだということを理解してもらってください。せっかく才能を持った優秀なアスリートが燃え尽きることなく、次のレベルに進んで成功をつかむことのできるようにリードしてあげてください。そのために専門家を積極的に活用してもらえればと思います」(ジョーンズ氏)
※
次のセッションでは、滝川クリステル氏をモデレーターに、ハーバード・メディカルスクールの研究者が登壇し「睡眠」の重要性を説いた。次稿へ続く。