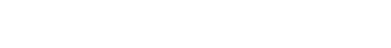現在、医療関係者だけでなく一般的にも関心が高まる「未病」。“まだ病気ではないが、健康でもない”という状態をいかに特定し、予防に役立てていくか。プロサッカー選手を引退後、腸内細菌の研究を行うAuB株式会社を経営する鈴木啓太氏が、東京大学名誉教授の合原一幸氏らと、アジア初開催となった「Sports Doctors Network Conference 2025」で語り合った。(全7回の7回目/第1回から読む)
健康と病気の間にある「未病」とは?
「未病」とは“まだ病気ではないが、健康な状態ともいえない状態”を指す。健康な状態と病気の間と考えられ、検査では異常が見られないが、なんとなく体調が優れない、疲れやすいといった状態も含まれる。
東京大学の名誉教授、合原一幸氏はこう説明する。
「未病は見つけるのが難しいんです。本人の自覚がない場合もあり、健康なのか未病なのかが区別できないこともある。そのため未病を客観的に評価するための指標、バイオマーカーを見つけることが重要です。病気になってから治すのは大変ですが、病気になる前に防ぐことができればいい」(合原氏)
生活習慣を良くするなど健康状態を保つアプローチが「健康医学」。そして健康状態から病気状態への移行を早期に検出して抑えるのが「予防医学」。健康医学から予防医学、そして病気を治療する「医療」への連携が求められている。

腸内細菌の研究で健康へのヒントを探る
鈴木啓太氏は日本代表としてもプレーした元プロサッカー選手。現役を引退後、2015年にAuB株式会社を興して腸内細菌の研究に取り組んでいる。
「2000年から2015シーズンまで浦和レッズで16年間、アスリートとしてプレーする中で、パフォーマンスを発揮するためにはコンディショニングが重要だということに気づいたのです」(鈴木氏)
トップアスリートの検体、つまりは便を集めて腸内細菌を分析・研究することで、サプリメントなどのコンディショニング製品への展開をすすめている。いわゆるフードテック企業にもなりつつある。「アスリートがコンディショニングをするデータを『民主化する』ことを目指しています」と鈴木氏。
現在ではトップアスリートのデータだけでなく、“長寿”や“健康寿命”を切り口にして別のアプローチも試みている。
「京都府京丹後市が長寿の町ということで、高齢者の方の便検体を集めて、同じ京都府の京都市内に住んでいる方と比較してみました。すると、京丹後市の高齢者の方のほうが、酪酸産生菌(※)が多かったんです。
また、マスターズ陸上で活躍する、70〜90歳のアスリートの方のデータも調べてみました。一般的に、加齢とともにビフィズス菌(※)が減っていくんですが、マスターズ陸上に出場されていた高齢者アスリートの方々は、一般の高齢者よりも減少率が低かったんです」(鈴木氏)
※ 酪酸産生菌もビフィズス菌も腸内に生息する善玉菌。共生関係にあり、酪酸産生菌は栄養源を分解して酪酸を生成することでビフィズス菌など他の善玉菌も棲みやすい環境にする。
研究成果を実社会に活かすために

こうした研究や調査結果が、今後、一般社会に活かされていくことになる。例えば、鈴木氏が現在取り組んでいるのが、「腸内環境を調べられるトイレ」の開発だ。
「現在、腸内細菌を調査する方法は、ほとんどが検便です。検体を送ってもらい、早ければ2〜3週間、長くて1ヶ月ほどの時間がかかります。詳しく調べるには仕方ないかもしれませんが、一般社会に実装するには、もっと簡単に結果を知りたいということになる」(鈴木氏)
つまり、一般人からしてみれば研究結果のような詳しいデータよりも、『自分の腸内の調子はどうなのか』を手っ取り早く知れたほうがいい。
「そこで今私たちが開発しているのが“腸内環境を調べられるトイレ”。菌が作り出した代謝物質の臭いを検知するセンサーをトイレにつけて、毎日の排便から腸内環境を調べる。病気になりそうな環境であれば、それに対してアラートをするような仕組みです」(鈴木氏)
実際に、製品化についても見通しが立ってきているという。毎日のトイレを通して自分の腸内環境がわかる。そうすると、健康、未病、疾病といった体の状態を判別することに役立てられる。
「この1年ぐらいでできる可能性があると考えています。アラートの精度を上げるには、さらに深く研究していかなければならないので、できる限りたくさんのトイレを設置して、毎日たくさんの検体が収集されていくようにできるといいですね」(鈴木氏)