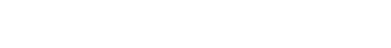サントリーとパナソニックは、両社ともにラグビーとバレーボールのトップチームを保有しており、日本における企業スポーツの代表格だ。リーグがプロ化に舵を切るなか、両社は企業が持つスポーツをどう捉え、いかに活用しようとしているのか?都内で開催されたスポーツビジネスカンファレンス「HALF TIMEカンファレンス2025 supported by アビームコンサルティング」で議論を交わした。
CSRから事業へ。スポーツの位置づけの変遷
「福利厚生」や「CSR活動」として捉えられていた企業スポーツだが、ラグビーやバレーボールでは、プロ化を目指す新リーグの誕生により、事業としての視点が求められている。
サントリーホールディングスの森田壮一氏は「創業者の鳥井信治郎の『事業で得た利益は社会に還元しなければいけない』という理念のもと、スポーツ活動もCSRの一環として長く続けてきました」と語る。そして「プロリーグが始まるタイミングで、これをCSRではなく事業として見るようになった」と転換のきっかけを明かす。
2021年にスポーツ事業推進部が新設され、25年1月にはスポーツ事業部となった。スポーツの位置づけが明確に変化してきている。

一方、パナソニック スポーツは2022年4月にパナソニック100%子会社として設立。社長の久保田剛氏は「パナソニックが事業会社制を導入するタイミングで、且つ、バレーボールやラグビーのプロ化の話もあったことから、自立した会社としてスポーツそのもので事業ができるように挑戦しようと立ち上げました」と話す。
パナソニック本社直轄の旧スポーツマネジメント推進室を事業会社として法人化、パナソニックの子会社だったJリーグのガンバ大阪の株式を移管して傘下とするとともに、ラグビー(埼玉パナソニックワイルドナイツ)、バレーボール(大阪ブルテオン)、パナソニック野球部、パナソニック女子陸上部を運営している。これにより、パナソニックグループ内で5つのチームを保有・運営する“スポーツ企業”となった。

スポーツの社内外の存在意義が問われている
スポーツを事業化するとはいえ、収益化は決して容易ではない。久保田氏は「例えば、ラグビーは保有選手が60人、スタッフを含めると100人近くになりますが、ホームゲームは年間8試合しかない。これだけで経営を成り立たせるのはかなり厳しい」と述べる。
バレーボールにおいても、SVリーグ発足後に外国籍選手の出場枠が増加。これまで1枠だったものが2枠、さらに今後は3枠になる見通しだ。「外国籍選手に1億、2億円の契約が増えていく中で、コスト増をどう吸収するかが課題」と、同氏は指摘する。
スポーツチームの存在意義を社内外に問われる中で、母体企業に依存する運営では限界がある。そのため、「今まではブランド部門や事業部門が我々(スポーツチーム)を使って何かを行う形でしたが、今は我々自身が、パナソニックの内外に価値を発信しています」と久保田氏は続ける。
試合の興行という点では既に一定の成果は出している。大阪ブルテオンは、昨年始まったSVリーグ初年度において、全ホームゲームで完売を達成。また、自チームには多くの人気選手や日本代表選手を擁しており、その強みを活かして、日本バレーボールへの人気が高い東南アジアへの進出も進めている。
一方、サントリーの森田氏は、「スポーツを事業として捉えてスタートはしたものの、まだスポーツ企業とまでは言えません」と前置きしながら、「本業への売り上げ貢献」「コーポレートブランドの価値向上」「社員の一体感醸成」の3点を軸に、社内でスポーツチームの存在意義を伝えているという。
「チームファン層は、一般消費者に比べて明らかにサントリー製品の購入額が高いというデータがある。また、ラグビーとバレーではファン層が異なるので、それぞれに合った商品連携も展開しています」と森田氏は語り、試合会場では商品販売やブース展開など、ファンとブランドを結びつける場としての機能を果たしている。

スクール・アカデミー拡大で地域に貢献
両社とも現在積極的に取り組んでいるのが、拠点地域でのスクールやアカデミーの拡大だ。企業スポーツは元来“社内貢献”が中心だったが、「今は外に出てスポーツの価値を発信しなければやっていけない。パナソニックグループもその方向を後押ししてくれています」と、久保田氏。
サントリーの森田氏は「昨年ラグビーのスクールを1校増やして2校に、バレーボールはもともと2校だったのを4校に拡大しました。地元の協力がなければ成り立たない取り組みで、集まってくる子どもたちにとっても非常に良い場になっています」と語る。
また同氏は「社員選手は引退後に社業に戻れますが、プロ選手はそうではありません。引退後にアカデミーで教えるというような受け皿を作ることも重要だと考えています」とアスリートのセカンドキャリア支援も視野に入れる。

パナソニックもスクール活動を積極的に行っている。
「ラグビーでは埼玉県と旧拠点の群馬県をまたいでスクールを展開しています。また、立正大学、東洋大学といった大学とも連携しています」(久保田氏)
大阪ブルテオンの拠点である大阪・枚方市では、複数チームを抱えるパナソニックならではの光景が見られるという。
「練習時間になると、ガンバ大阪や大阪ブルテオンのユニフォームを着た子どもたちが、自転車に乗って集まってくる。我々は複数の競技を保有し、複数の施設も運営しています。部活動の地域移行も進んでいますし、こういった資源を地域で有効活用できれば、地域の方々からも応援してもらえると思います」(久保田氏)
※
セッションでは、「社内の福利厚生的な存在だったスポーツチーム」が「事業を行うスポーツチーム」へと変化していく姿が鮮明に語られた。その潮流の真っただ中にある両社の取り組みに、今後も注目が集まる。
カンファレンス・アーカイブ動画
カンファレンスのセッション「企業によるスポーツ活用の現在地」のアーカイブ動画(全編ノーカット版)をご覧いただけます。以下のフォームからアクセスください(無料)。