スポーツ庁が2019年から展開するスポーツと他産業の共創を目指すアクセラレーションプログラム『SPORTS BUSINESS BUILD』。約50の応募から選考を経て採択された4プロジェクトのうち、今年2月に行われたDEMO DAYで最優秀賞を受賞したのが、東商アソシエート、大日本印刷(DNP)、パナソニックによるハンドボールの新たな体験コンテンツだ。3社のコラボレーションについて、企業連携のカギと今後の展開を聞いた。
新サービス開発、「投げる楽しさ」にフォーカス

小学生の頃、休み時間にドッジボールで遊んだことのある人は多いはずだ。授業が終わるのを今か今かと心待ちにし、チャイムとともに校庭へ駆け出す――。ボールを投げる遊びは、誰しもの原体験と言える。
このシンプルな遊びを体験コンテンツに昇華させ、ハンドボールの普及につなげようとしているのが、東商アソシエート、DNP、そしてパナソニックだ。
3社は、スポーツ庁が昨年9月から展開する、スポーツと他産業の共創で新サービス創出を目指す『SPORTS BUSINESS BUILD』に参加。「フィジカル×デジタル×遊び」をコンセプトに、プロジェクションマッピングを活用したハンドボールの新たな体験コンテンツを開発した。2月のDEMO DAYのプレゼンテーションでは「ハンドボールの競技人口を増やしていく上でインパクトがある」と審査員から評価を受け、見事、最優秀賞を獲得するに至る。
DEMO DAYの会場ではデモ機もお披露目。プロジェクションマッピングとセンシングが施された壁面にハンドボールのボールを投げると、得点などが加算されるというゲーム性のある体験コンテンツは、多くの来場者の関心を集めた。
取り組んできたプロジェクトが認められたことについて、東商アソシエート株式会社 取締役 クライミング&アミューズメント事業部事業部長の滑川建佑氏は、「昨年11月から3社でかなり打ち合わせをしてきた。その結果が出たのですごく嬉しかったですね」と喜びを表現する。
パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 サービスインテグレーション本部 IoTサービス部の野中隆志氏は、最優秀賞という結果はもちろん、3社で取り組めたことに手応えを感じているようだ。
「今回、(ハンドボールという)スポーツをどう盛り上げるかを一番に考えるにあたって、キーになったのは3社でできたところです。1社だと色々と制限があったりするので、お互いの良いところを強調してできたことが一番大きかったです」
大日本印刷株式会社 コンテンツコミュニケーション本部 コミュニケーションビジネス開発部 スポーツビジネス課の東恭平氏もうなずく。
「最優秀賞を目指すというよりも、何かしらプロダクトができたらいいなという位置づけで、DEMO DAYの機会をいただいた時点で満足はしていました。それでも、(最優秀賞として)認められたことで今後の販売にもつながりますし、協力いただいた2社にはひとつ貢献できて嬉しく思います」
企業連携の背景にあった、人と人のつながり

ハンドボールを舞台に日本を代表する企業によるコラボレーションが実現したわけだが、これにはどのような背景があったのだろうか?
滑川氏は、「このプロジェクトの前にDNPさんと弊社で、スポーツに関わる新しいことに取り組んでいきたいという考えがあった」と振り返る。同氏は元々DNPで勤務しており、東氏は当時の後輩だった。
二人が「スポーツで何か新しい仕事を作ろうよ」と事業を模索する中で、今回のスポーツ庁と日本ハンドボール協会の取り組みを知り、東氏が関係性を築いていたパナソニック野中氏も交えると、「じゃあやってみよう」と意見が一致。協業がスタートすることになった。
スポーツで何か新しいことを——。そう話す滑川氏が所属する東商アソシエートは、クライミングウォールの設計・施工で国内シェア70%以上を誇る業界リーダーでもある。元々は貿易会社として創業し、クライミングに進出した同社の発展について、滑川氏は次のように語る。
「(会社は)74年前の1946年に始まって、様々なアイテムを貿易で扱っていました。その中でフィットネス器具を輸入して、日本に販売する部隊ができたのが約30年前です。海外の展示会でクライミングというものがあるから日本に輸入してみない?とクライミング用品を輸入したのが最初だったんです」
その後、輸入・販売だけでなく自社で設計・施工も手がけることとなる。当時はクライミングの認知度は決して高くなかったが、ここ10年で世の中に浸透したという。
「(2008年の)リーマンショックの後、手軽にできるスポーツが求められてきて、クライミングはこの10年で認知度が上がってきました。遊具や公園といった子どもたちが遊べる場が少なくなり、そういった施設が望まれるようにもなりました。民間のクライミングジムだけでなく、ショッピングモールや学校の体育館など、分野を問わず施設を作るというお話をいただくようになりました」
さらに2013年には、東京がオリンピック・パラリンピックの開催都市に決まり、スポーツクライミングが新種目に選ばれたことも追い風となった。「五輪に選ばれるのと選ばれないのでは、全然違ったと思うんですね。選ばれたことでメディアに出る機会もかなり増えました」と、滑川氏は実感を口にする。
このハードに強みを持つ東商アソシエートに、コミュニケーションを領域とするDNP、そしてデジタルテクノロジーに強みを持つパナソニックが参画して、プロジェクトが形作られていった。
DNPとパナソニックがスポーツに注目するワケ

協業をするに至ったDNP東氏が所属するのは、社内に新設された「スポーツビジネス課」。東京2020大会などを見据えたのはいうまでもなく、同氏も「名前に『スポーツ』がついた部署は(DNP内で)珍しく、新しい展開を感じる」と話す。とはいえスポーツが領域となっても、これまで培ってきた企業の強みを活かすことには違いない。
「印刷会社としては、スポーツの力を借りて“コミュニケーション作り”を支援していくのが役割です。今の時代は、『その商品が好きだから』という消費者との共感の時代です。プロモーションやイベントをするにしても、単に商品を配りました、チラシを撒きましたではなく、コンテンツとセットで記憶に残していただき、思い出にしていただく。そうしたプロモーションは、スポーツと相性がいいと思います」(DNP・東氏)

もう一つの協業パートナーであるパナソニックは、映像や音響をコア技術の一つに持ち、スポーツではスタジアムソリューションを提供する。新国立競技場の大型映像設備や音響設備に代表されるハードも提供するが、現在注力するのはプロジェクションマッピングや高速のトラッキング技術など、映像処理・解析のソフト分野だ。
野中氏は次のようにも、スポーツの現場で活用される、パナソニックのテクノロジーの一端を紹介してくれた。
「去年のバレーボールのワールドカップで、3Dトラッキング技術を導入したんです。速度を測るというのは以前からありましたが、(ボールの)軌道だったり、(選手が)どのくらいの打点の高さから打っているかなどを映像解析する仕組みです。映像をただ見る、音声をただ聞くだけではなく、プラスアルファを追究しています」
コンテンツは、わかりやすさ・楽しさ・ゲーム性

こうして、ハンドボールを題材に3社がサービス開発をしていくこととなるが、東氏が着目したのは、ボールを投げるという動作のシンプルさ、それで得点を競い合う競技の分かりやすさだった。これには、SPORTS BUSINESS BUILDの一環で昨年11月に行われた、ハンドボールの試合視察も参考になったという。
「ハンドボールの“わかりやすさ”は、コンテンツの広がりと競技の普及の両立につながるのではないかと思いました。無理にハンドボールを広げるのではなく、こういう(ボールを投げるという)スポーツ体験を広げていくと、自然とハンドボールをやる人が増えていくんじゃないかと」(DNP・東氏)
次に着目された要素は「楽しさ」と「ゲーム性」だった。滑川氏が、「初心者や子どもたちにいかに楽しんでもらうか、入り口をどう広げてあげるかが重要」と指摘するように、スポーツ体験を広げるには、取っ掛かりやすい仕掛けが必要だった。ゴールが映し出された壁に向かってボールを投げると、得点を競い合って遊ぶことができるという機能は、まさにそれを実現するものだ。
これについては野中氏も、「プロが投げても子どもが投げても、ポイントで競う形にしました。場合によっては子どもが勝つこともあるので、ゲームをみんなが楽しめる。そういった観点から、ゲーム要素を強くしました」と狙いを語る。
最後に重視されたのは、展開のしやすさだ。ポータブル性を備えることで、様々な場所で設置が可能になると、その分、生活者との接点が増えることにもつながる。
「持ち運びができ、どこでもできるというのをコンセプトに掲げるべきかなと思っていました。それを見た人が自分でもやってみたいとか、自分でもできそうだと感じてもらう必要があるなと」(DNP・東氏)
誰でも気軽に楽しめる形を作り、なおかつどんな場所にも設置できる。ハンドボールの試合会場はもちろん、ショッピングモールの一角に置くことも想定している。
ハンドボールの国内の競技人口は約10万人。裾野を広げる意味で、遊びやゲーム性という要素が興味を持つきっかけになるだろう。子どもたちに楽しんでもらい、ハンドボールを身近に感じてもらうことができれば、長期的に見ると競技人口の増加にもつながってくる。そうしたイメージを描きやすい点も、今回のプロジェクトが評価された点だ。
新たに発見した、企業連携のカギ

3社は今回のプロジェクトで、企業連携に関する新たな発見があったという。東氏が挙げたのは、大企業ならではの障壁をいかに乗り越えていくかという点だ。
「どの企業でも、アイデアが思い浮かんでもアクションに移せないことが往々にしてあると思うんです。『こういうのできたら面白いよね』という話は出るんですけど、実際にそれを作るとなると、費用や稟議などでストップがかかってしまう。なので、今回のようなコンペティションは動きやすかった」
こう話す東氏は、新サービスの開発で足かせになりやすいボトルネックも指摘する。
「今回は、会社としての命令が出て参加したわけではなくて、個人個人のボトムアップで形にさせてもらった。なので、『絶対これでマネタイズしなければいけない』といった縛りがなかったのは、良かったところですね(笑)」
滑川氏もこれに同調して、サービスを考える「純粋さ」が今回のポイントだったと振り返る。
「こういった企業連携では、会社を背負って来てしまうと、うまく進まないことがあって(笑)。今回は全然違う分野の人が集まって、お互いが言いたいことを言って進められた。純粋に、ハンドボールをどう楽しむかをみんなで考えられたんだと思います」
この「損得勘定」については野中氏も深く頷きながら、自主的でボトムアップな企業連携は、新しい働き方にもつながるのではとの見方を示す。
「損得勘定抜きにできたことが一番良かったです。自社だけでやるのではなくてコラボレーションという形もあることを、今回の結果を受けて社内に紹介できれば良いですし、今後のビジネスのやり方として、こういった(ボトムアップの企業連携の)形が一般的になってきたら、楽しいと思いますね」
各社が強調していたのは、自社だけではここまで辿り着けなかったという点だ。企業連携で知見を出し合い、議論を重ねることで成果が生まれたと口を揃える。一人ひとりがボトムアップで進めたからこそ、純粋な気持ちでプロジェクトと向き合うことができた。
今の時代、企業連携そのものが珍しいわけではなくなってきたが、企画を成功させるより問題なく進めるという「事なかれ主義」が蔓延し、いつの間にか目的が変わってしまうケースも散見される。その点、個人の自主性により始められた今回の取り組みは、3社にとって意義深いものとなったのだろう。
リアル×デジタル 今後の可能性は
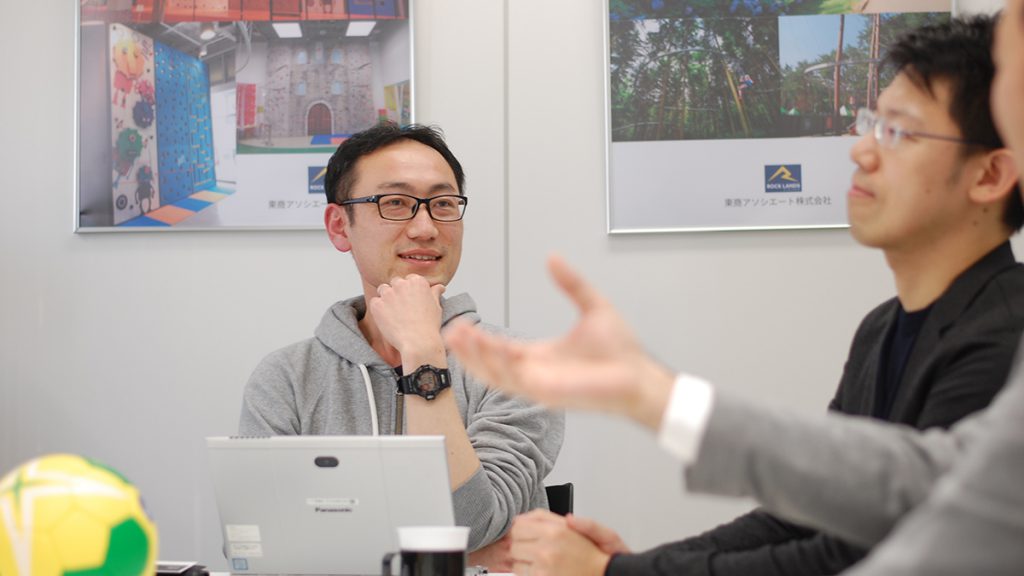
今回、3社のプロジェクトは「投げる」という単純明快な動作をベースに、誰もが楽しむことができるコンテンツを提案した。シンプルだからこそ様々な形に応用可能で、可能性は広がるばかりだ。インタビューの最中にも、どんどんアイデアが飛び交う。
例えば、ボールを投げる際にセンサーでフォームを読み取る技術は、競技者にとっては自身の投げ方を確認し改善することにつながる。初心者であれば、トップアスリートの見本を真似することで上達が早くなり、さらに楽しめるはずだ。
野中氏は「先の話にはなるんですけど」と前置きしつつ、「センサーの機能を使って、その人に最も向いているスポーツも示せるようになれば面白い」と話す。
これはヘルスケアやリハビリにも用いることができるだろう。肉体的にも精神的にも負荷のかかるリハビリも、ゲーム性を加えることで楽しい気持ちで行えるのではないか、というのが東氏の意見だ。
「ただ腕の筋肉を鍛えるだけだと面白くないので、10ゲームやりましょうとか5000点取ってくださいとか目標を変えると、ヘルスケアの意味も変わってくると思います」
ハンドボールはもちろんのこと、さらに先に目線を上げて話す3社。それは、最優秀賞がゴールではなく、ここからがスタートであることも物語っている。
可能性が広がる未来について、終始、楽しげな口ぶりや表情を見せる彼らの姿。それはまるで、ボールを持って校庭に飛び出していく、少年たちのようでもあった。





