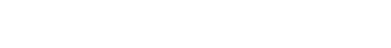欧州スポーツ界では、スタジアムの役割が急速に変化しています。単なる競技場ではなく、ファンにとっての「体験装置」として再定義されつつあるのです。この変化の本質は何か? そして、どうすれば日本でもスタジアムにおける体験価値を最大化できるのか?
今年9月開催の「World Football Summit(WFS)香港」にあわせ、WFS日本市場代表の堀口創平氏が解説する、欧州・アジアのスポーツビジネストレンドの第2回をお送りします。(文=WFS堀口創平氏)(全4回の2回目/第1回を読む)
ベニューとは何か? なぜ今、注目されているのか?
欧州サッカー界でこれまで「スタジアム」や「アリーナ」と呼ばれていた空間は、近年「ベニュー(venue)」という言葉で語られるようになってきました。その理由は、クラブがスタジアムを単なる試合会場としてだけではなく、ファンとの関係性を築き、日常的に価値を届ける「体験装置」として捉え始めているからです。
たとえば、ある日には試合が行われ、別の日にはツアー、ミュージアムでの展示、また別の日には地域イベントやスポンサーの発表会や企業セミナーが開催される。さらに、イベントのない日でも家族連れや観光客が訪れ、グッズを購入したり、スタジアム内のカフェで過ごす。そうした、多機能な「目的地」としての役割を果たすケースが増えているのです。
こうした背景から、「ベニュー」は今やクラブの経営戦略の中心に位置づけられつつあります。競技、文化、商業、社会が交わる場としての“クラブの顔”――それがベニューのあるべき姿なのです。
ベニューの役割を示す「4つのリング」フレームワーク
そうした現代のベニューが担う役割を明確化しようと、スポーツ専門コンサルティング会社のSPSGコンサルティングでは「4つのリング(The 4 Rings)」というフレームワークを提唱しています。
これはベニュー体験を4つの層に分けて分析するもので、ピッチからグローバルなデジタル接点まで、現代のベニューが担う役割を明確化することに役立てられます。

- リング 1 「ピッチ」:ピッチ上の試合体験(試合そのもの、雰囲気、ハーフタイム演出など)
- リング 2「スタジアム」:会場(スタジアム)の空間設計(座席、導線、飲食、テクノロジー、施設体験など)
- リング 3「地域社会」:地域社会との関係性(地元住民、アクセス、地域文化、行政連携など)
- リング 4「世界中のファン」:世界中のファンとの接点(デジタル施策、SNS、グローバルイベントなど)
リング1「ピッチ」:体験の魂
スタジアム体験の中心にあるのは、やはりピッチ上の試合そのものです。ファンが求めているのは勝敗だけではなく、選手の躍動、スタジアムの空気感、歓喜と落胆の感情体験といった“魂の震え”です。デロイト社の調査でも、スタジアム体験におけるファンの期待のうち、「質の高いゲーム」と「雰囲気ある空間」の2つが最上位に挙げられています。
具体的には、以下の要素がこの核となる体験を構成します。
- ピッチ上の試合クオリティとインテンシティ
- 応援(コレオグラフィー、チャントなど)の一体感
- ハーフタイム中の演出(音響・映像・コンテンツ)
- 感情のマネジメント(試合展開に応じた空気作り)
例えば、スウェーデンのマルメFFは、こうした演出に長けたクラブで、世界的に評価されるコレオグラフィー文化と一体化した試合演出に定評があります。また、ハーフタイムにファンの導線をコントロールする施策や、試合内容に応じてスポンサーや演出チームが演出を切り替える動的な設計も重視されています。
リング2「スタジアム」:物理的な器
スタジアム体験を提供する「器」として、スタジアム空間・施設全体の快適性と機能性が問われます。清潔さ、利便性、飲食、座席設計、テクノロジー対応、バリアフリー対応など、ピッチ以外の要素がファンの満足度を大きく左右します。例えば、以下の項目です。
- 飲食店やサービスの質と導線(混雑の緩和、モバイルオーダー対応など)
- 座席構造と視認性、アクセスのしやすさ
- AR・VR演出やスタジアムWi-Fiの整備
- 聴覚・視覚・身体に配慮したアクセシビリティ設計
こうした中、注目されているのがスタジアムデザイン会社Molca Worldの「パズルピース型改修」というアプローチです。これは、スタジアム全体を一気に改修するのではなく、ファン体験に影響の大きいエリアを戦略的に選び、段階的に改修していく手法です。
例えば以下のような部分的な改修で大きなインパクトを狙うものです。
- ゴール裏エリアの演出強化:応援文化を育むため、立ち見エリアの改装やバナー設置スペースの整備
- 座席間の導線・動線の整理:混雑を緩和し、移動ストレスを軽減
- VIPゾーンのアップグレード:ホスピタリティ強化による新たな収益源の創出
このように、パズルのピースのように一つひとつの改修を積み重ねることで、大規模改修が難しいクラブでも、体験価値を確実に高めていくことが可能になります。実際にMolca World社では、ジローナFC(イタリア)やRCDエスパニョール(スペイン)といったクラブに対して、各クラブの事情に合わせた改修提案を行い、高い評価を得ています。
リング 3「地域社会」:支える土台
スタジアムは、単体で完結する空間ではありません。むしろその地域の文化、交通、飲食、観光資源、住民の協力など、「まち」との関係性全体がファン体験を構成します。こうした体験設計においては、以下の点が重要になります。
- スタジアム周辺の利便性・治安・観光資源
- 地元の飲食店やショップとの連携
- 行政・企業・教育機関とのパートナーシップ
- ファンの「到着前」から始まる体験ストーリーの設計
CDレガネス(スペイン)は、こうした地域との関係性を軸にスタジアム戦略を展開しているクラブです。レアル・マドリードなど、同じマドリード州内のビッグクラブと差別化するため、地域に根ざしたクラブの姿を打ち出しています。
リング4「世界中のファン」:影響力の拡張
デジタル時代においては、スタジアムに来場できないファンともつながることが必須です。SNS、ストリーミング、デジタルイベントなどを通じて、世界中のファンにクラブ体験を届ける設計が問われています。
この戦略は、以下の4ステップに整理されます。
- Learning:国・文化ごとの嗜好を理解する
- Communicating:情報を適切に届ける
- Activating:デジタル・現地イベントで共感を創出する
- Connecting:ファン同士とクラブとの帰属意識を育む
この領域の代表格がマンチェスター・シティです。シティ・フットボール・グループの国際展開に加え、SNS運用、戦略的なアカデミー配置、デジタルの活用により、2024年時点でサッカークラブとして世界第5位のフォロワー数(前年比+2750万人)を記録。さらに、海外でのファンゾーン運営など、世界中のファンとの物理的・心理的な距離を縮めることに注力しています。
包摂性・持続可能性・革新性が未来のスタジアムをつくる
以上の「4つのリング」に加え、すべてのリングを貫く重要な要素として以下の3つが挙げられます。
- 包摂性(Inclusivity):ジェンダー、障がい、文化的多様性に配慮した設計
- 持続可能性(Sustainability):成績や経済的制約を乗り越える長期視点
- 革新性(Innovation):デジタルに限らず、新たな体験様式の創出
改めて、スタジアムはもはや施設というだけでなく、クラブの経営・戦略・文化が具現化された「体験の場」となっています。どのリングをいかに強化するのか。その判断が、今、求められています。
※
次回は、ファン・エクスペリエンスのフレームワークを紹介し、どのように顧客体験を設計し、最適化していけるかを紹介します。
「World Football Summit」が9月に香港で初開催!
2025年9月3日(水)〜4日(木)、香港で、東アジアで初となる「World Football Summit」が開催。スポンサーシップ、メディア、テクノロジー、ファンエンゲージメント、投資などをテーマに世界のサッカービジネスをリードするキーパーソンが集結。海外サッカークラブと新たなビジネスチャンスを見つけたい方、グローバルトレンドをいち早くキャッチしたい方には見逃せないイベントです。https://worldfootballsummit.com/hong-kong/