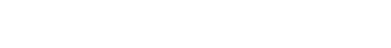BMXとは、Bicycle Motocrossの略称で、1970年代初頭にアメリカ西海岸を中心に流行った子供たちが自転車を乗り回す遊びから始まったもの。
BMX競技にはレースとフリースタイルがありますが、フリースタイルが東京オリンピックで新種目として採用されたことから注目を集めています。
本記事では、BMXに用いられる自転車はどういうものなのか、その特徴と一般の自転車との違いについて紹介します。
BMXで用いられる自転車の特徴
BMXは、大きく分けて2種類の競技に分けられます。
1つは、選手が全長400メートルほどの様々な形状のコースを一斉に走り、着順を競う「レース」、もう1つは、自転車を使っていろいろな技を繰り出し、その難易度や独創性を競う「フリースタイル」です。
それぞれの競技で用いられる自転車の特徴を解説します。
レース競技での自転車
レース競技は「速さ」が求められるもの。
そのため、レース競技に用いられる自転車は、軽量で、ある程度の強度を持ったアルミニウムやカーボンなどを素材として使用します。
また、レース競技での自転車は「レーサーBMX」とも呼ばれます。
フリースタイル競技での自転車
フリースタイル競技は、制限時間内に技を入れた演技をして、ジャッジによるポイントで順位が決まるもの。
どこでライディングするかによって、フラットランド、パーク、ストリートに細分化されます。
フラットランド用の自転車
フラットランドは、平らな地面で足を地面に着かないように様々な技を連続して行う競技。
前後車輪の左右に突き出したペグの上に立ったり、バランスよくハンドルやペグを使って自転車を回転させたり、ダンスのように巧みに自転車を操ります。
大きなジャンプは行わないので、全体的には細めのパイプでコンパクトに出来ている自転車が用いられます。また、立って技を行うことが多いため、装着するペグには靴が滑らないような加工がされているものが使われます。
パーク用の自転車
パークは、スケートボードパーク施設の大きなジャンプ台で大技を決めることが中心となる競技です。
ジャンプが中心となるため、着地の衝撃に負けない頑丈な作りであることが必須となりますが、自転車自体はできるだけ軽くすることが重視されるため、ペグを省くライダーもいます。
パーク専用の自転車のタイヤには、ストリートよりもやや細めで溝の浅いものやセンター部分に溝のないものが好まれます。土でできたジャンプコースなどを走るトレイルライドに使用する場合には、前輪が着地で滑らないように溝の深い太めのタイヤが用いられます。
ストリート用の自転車
ストリートは、街中や公園にある縁石や手すり、壁などの人工的な構造物を使うもの。
段差を利用して飛んだり、ペグを階段の手すりに引っかけて滑らせたり、壁にタイヤをバウンドさせたりして技を競いあうものであり、ジャンプすることも多いため、着地負担を考えて太めのタイヤと頑丈な車体である自転車が好まれます。
使われるペグには、縁石を滑らせたり、引っ掛けたりすることができるよう、鉄製やアルミ製のもので樹脂製のカバーがついているものが使われます。
BMXと一般の自転車との違い

BMXと一般の自転車とを
- 素材
- ブレーキレバー
- リアハブ
- サドル
- ギアチェンジ
- タイヤ
- ペグ
- ジャイロとハンドル
の項目別に比べていきます。
素材
一般の自転車に用いられる素材で多いのが、安価ではあるものの錆びやすく重いのが特徴として挙げられる「スチール(鉄)」です。
一方、BMXは、車体の軽量化のためにアルミやカーボンなどの素材や、鉄の中でもある程度の柔軟性のあるクロムモリブテン鋼(クロモリ)やハイテンシル鋼(ハイテン)などが使われます。
ブレーキレバー
一般的に、自転車のブレーキレバーは右が前、左が後ろのブレーキとなりますが、BMXは、一般自転車と異なり、右ブレーキレバーが後ろブレーキ、左が前ブレーキとなります。
また、BMXにブレーキを付けないライダーも多く見かけます。
リアハブ
BMXのリアハブにはカセットハブとフリーコースターハブ(フリコ)とがあります。
カセットハブは、コグというパーツに爪が付いていて、その爪がハブの歯車に引っ掛かることでハブが回転するものであり、引っ掛かることで発生するラチェット音が好きというライダーも多いようです。
一方、フリーコースターハブは、進行方向と逆方向にハブを回してもコグの部分は回らないというもの。つまり、後ろ向きに走る動きになった時にクランクを回すことなく後ろに進むことができます。タイヤの走っている音や感覚をよりダイレクトに感じたい人におすすめです。
ハブの選択には、やれる技の種類や技のやりやすさも関連してくるので、自分のやってみたい技に合わせて選ぶとよいでしょう。
サドル
BMXではサドルに腰掛けることはあまり意識されていません。そのため、サイズはごく小さく、ライディングの際に邪魔にならないよう、前上がりに低くセッティングされています。
ギヤチェンジ
BMXには、一般の自転車にあるような変速機は装備されません。
タイヤ
一般の自転車では、24インチや26インチのタイヤが使われますが、BMXでは幅5センチ前後、20インチの小回りの利く小さいタイヤが一般的です。
溝の深さや形状によって性能が違うため、ライディング場所に応じて選ぶと良いでしょう。
ペグ
フリースタイルBMXでは、長さ10センチ程度の金属製のペグと呼ばれるパイプを前後車輪の左右に4本(または、左右片側の前後に2本)取り付けます。
このペグは、フラットランドでは、手で掴みやすいように軽量で加工しやすいアルミやプラスチック製のものが用いられます。
一方、パークやストリートでは、構造物や縁石などに引っ掛けたり、滑らせたりするため、ある程度の強度と摩擦抵抗が必要となるため、鉄やアルミの金属、金属にプラスチックを被せたものが一般的に用いられます。
ジャイロとハンドル
BMXでは、ハンドルをくるくる回す技が使われますが、その際にブレーキケーブルがハンドルに絡まないような装置として、ジャイロと呼ばれる装置が取り付けられます。ハンドルバーは高めで、補強の入ったクロスバーという専用タイプが使われます。
BMX自転車の選び方
BMX自転車を選ぶポイントは、下記の4つ。
- ライディングスタイル
- 身長
- 人気
- 街乗り
それでは、詳しくみていきましょう。
ライディングスタイルで選ぶ ~レースかフリースタイルか
BMXの種目には、スピードを競うレースと技の難易度や表現力を競うフリースタイルとがあります。
まずは幅広く使えるようなタイプの自転車を選び、乗り慣れてきたらパーク&ストリートやフラットランドなどの専用自転車に移行して行くとよいでしょう。
身長で選ぶ 〜トップチューブ(TT)とチェーンステイ(CS)
フリースタイルのBMX選びで重要なのは、トップチューブ(TT)という本体の軸となる部分のパイプの長さですが、これは使う本人の身長でほぼ決まります。
フラットランドの場合、身長が150センチ台の方はトップチューブが18.0インチ前後、身長が160センチ台の方はトップチューブが18.5インチ前後、身長が170センチ台の方はトップチューブが19.0インチ前後のものがおすすめです。
パーク&ストリートの場合、身長が150センチ台の方は20.0インチ前後、身長が160センチ台の方は20.5インチ前後、身長が170センチ台の方は21.0インチ前後のトップチューブのものがおすすめです。
また、チェーンステイ(CS)と呼ばれる本体後方のパイプの長さは、乗り方を基に選ぶとよいでしょう。目安としては、パークを中心に選ぶには13.75インチまで、ストリートを中心に選ぶなら13.5インチまでとなります。機敏な動きを求めるなら短め、大きなジャンプを目指すなら長めが安定します。
ハンドルバーは、身長170センチまでなら8.5から9インチ、180センチまでなら8.75から10インチがよいでしょう。
人気で選ぶ 〜街乗りに向いているおすすめのBMX自転車
上記で紹介した方法以外に、人気で選ぶという方法もあります。
街や雑誌で見かけて「かっこよい」と思えるようなBMX自転車を選ぶのもよいでしょう。
ここでは、人気のあるおすすめのBMX自転車を紹介するので、ぜひご活用ください。
おすすめのBMX①|H-STREET
「H-STREET」は、ライフスタイルに合った自転車を提案しているDURCUS ONE(ダーカスワン)が、街に最も適するBMXとして作ったもの。男性女性問わず、かっこよく街乗りすることができます。
デザインがオシャレなだけでなく、ハンドルバーが高く、誰でも扱いやすいというのも魅力です。
おすすめのBMX②|Erro UTB
「Erro UTB」は、自転車のトップブランドの1つでもあるSUBROSA(サブローサ) が手がけたBMX。オンロードもオフロードもハイスピードで快適な走行が可能で、長距離でも快適に走行できます。
フレームはSサイズ(47cm)やMサイズ(52cm)、Lサイズ(54cm)の3サイズだけでなく、さらに小さなXSサイズと最も大きなXLサイズがあります。
Erroは速度を念頭に置いたタイプで、他に耐久性を重視したRixaというモデルも存在します。
おすすめのBMX③|The Roots
「The Roots」は、王道スタイルのものを選びたい方におすすめ。BMX創成期といわれている1970年代から1980年代前半にかけてBMXを、独自のスタイルで知られているブランドのHOW I ROLL(ハウアイロール)が現在に再現したBMXです。
現在では考えられないほど細いオールスティール製のフレーム、リメイクされたハンドルバー、MXレプリカのブレーキレバーとサイドプルブレーキなど、数々の魅力が満載です。
おすすめのBMX④|DEVOTION
「DEVOTION」は、Robo(ロボ)の愛称で世界中のライダー仲間に親しまれるRobbie Morales(ロビー・モラレス)が立ち上げたブランドであるCULT(カルト)のBMX。レトロな外観に加え、スリーピースクランク、ブイブレーキなどのクールな機能が満載です。
街乗りしたい方におすすめです。
おすすめのBMX⑤|MACH ONE PRO 20
「MACH ONE PRO 20」は、BMXの発祥メーカーであるGT(ジーティ)の原点であり、伝説を刻み続けているBMX。手軽に購入できる価格であることに加え、軽量なのに丈夫なアルミニウム製のフレームや、激しいライディングにも耐えうる頑丈なクランクを搭載しています。
本来はレース向きですが、軽量で推進力が高いので、カスタムすることで街乗りに適したBMXにすることも可能です。
まとめ
今回は、BMX自転車の特徴や選び方について解説してきました。
東京オリンピック2020の競技としても注目されたBMX。競技の種類や技の種類によって自転車が異なることから、どんな自転車を使用しているのか気になった方もいることでしょう。
本記事で紹介している選び方を参考にして、ぜひお気に入りのBMX自転車をお探しください。
(TOP写真提供 = Jan Kopřiva / Unsplash.com)
《参考記事一覧》
世界一カッコいい街乗りBMXありました GTヘリテージ(RITEWAY)