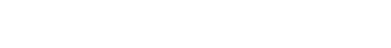落とそうと努力をしているのに、どうしても落ちてくれない浮き輪肉。1度ついてしまうとなかなか落ちてくれません。
そんな浮き輪肉を落とすためには、まずついてしまう理由と原因を知っておくことが大事です。
本記事では、浮き輪肉がつく原因や落とすために役立つおすすめのエクササイズなどを紹介しています。
頑張っているのに、どうしても落ちないことに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
浮き輪肉とは?
お腹周りについているぜい肉のなかでも、まるでお腹に浮き輪を付けたような状態の脂肪が「浮き輪肉」です。
一般的な浮き輪に見立てて、浮き輪肉と呼ばれていますが、そもそも浮き輪肉の原因は皮下脂肪です。
浮き輪肉は見た目の美しさだけでなく、健康にも悪影響を与える可能性があります。腹部に脂肪が集まることで内臓脂肪が増え、メタボリックシンドロームや心血管疾患、2型糖尿病などのリスクが高まる可能性があります。
どうして浮き輪肉になってしまうのか
一般的には、ぜい肉がついてしまう理由として多いのが食事の過剰摂取や野菜不足、運動不足などが挙げられます。
それでは、どうして浮き輪肉になってしまうのでしょうか。
浮き輪肉がつく理由としては、下記5つの内容が挙げられます。
- 加齢による基礎代謝の低下
- お腹周りの筋肉不足
- 慢性的な運動不足
- 日々の姿勢が悪い
- 消費より摂取量の多い食生活
それぞれについて、詳しく解説していきます。
加齢による基礎代謝の低下
人体は、基礎代謝によって、何もしなくてもエネルギーを消費しています。
しかし、加齢によって基礎代謝が低下すると、何もしなくても消費されていたエネルギーが消費されなくなります。
浮き輪肉も同様。その結果、消費されなかったエネルギーが、脂肪として蓄積されていきぜい肉となってしまいます。
前述したように、最初にぜい肉がつく部位はお腹です。
そもそも、加齢によって基礎代謝が低下する主な要因は、骨格筋量の減少。また、各臓器における代謝率の低下も要因として考えられています。
お腹周りの筋肉不足
筋肉不足によっても基礎代謝は低下します。
筋力の低下によって、燃焼部位が減少することが理由の1つ。スポーツをしていなければ、特に筋肉を鍛える必要はないと考えている方も、なかにはいることでしょう。
しかし筋肉不足となると基礎代謝が落ちてしまい、消費されなかったエネルギーが脂肪として蓄積されていき、浮き輪肉となってしまいます。
そして、最初にぜい肉がつく部位はお腹。筋肉は体温をつくり出す働きを担っているため、筋肉量が減った部位は、体温が低下しやすくなるのです。
そうなると体はその部位の体温がこれ以上、下がらないようにするために、保温機能の高い脂肪で埋めようとします。
お腹周りが筋肉不足に陥っている場合、その流れがお腹周辺で起きてしまい、保温のために埋めた脂肪が浮き輪肉となってしまうのです。
慢性的な運動不足
一般的には、何もしなくても基礎代謝によってエネルギーは消費されていますが、運動することでよりエネルギーは消費されます。
そのため、運動をしていれば消費されなかったエネルギーが浮き輪肉のようなぜい肉になることはありませんが、1日の運動量が足りていない場合は浮き輪肉の原因となり得ます。
また、運動不足は筋肉量の低下も招くため、注意が必要です。
日々の姿勢が悪い
何かに没頭していると、つい姿勢が悪くなりがち。姿勢を正した状態を続けるには、常に筋肉を使う必要があります。
猫背のような悪い姿勢が楽な理由は、筋肉を使っていない状態のため。日々の姿勢が悪いと、日々筋肉を使わないような構造になっているため、筋肉量が低下します。
また、筋肉を使うということはエネルギーを使うということに繋がるため、日々の姿勢が悪いと消費するエネルギーが減少します。
その結果、消費されなかったエネルギーが脂肪として蓄積されていき、浮き輪肉となりやすいことは留意しておかなければなりません。
食生活の悪化
体内で消費されるエネルギーよりも摂取エネルギーが多い状態が続くと、消費されなかったエネルギーが脂肪として蓄積されます。
消費されるエネルギー量は、常に一定ではなく、「年齢」「筋肉量」「運動量」によって変わります。
食生活の悪化により、消費エネルギーと摂取エネルギーを意識できない環境が、浮き輪肉に繋がることは留意しておかなければなりません。
浮き輪肉落とす方法は?
浮き輪肉を減らすためには、皮下脂肪を減らすことが必要です。
適切な食事管理
バランスの取れた食事を心がけましょう。食事中心を野菜や果物、質の良いタンパク質(鶏肉、魚、豆類など)にし、脂肪や糖分の摂取を制限します。また、食事の量をコントロールするために食事の時間をゆっくりと過ごし、満腹感を確認しながら食べることも重要です。
適度な運動
有酸素運動や筋力トレーニングを取り入れることで、脂肪燃焼を促進し浮き輪肉を減らすことができます。有酸素運動としては、ウォーキング、ジョギング、サイクリングなどを選ぶと良いでしょう。また、腹筋やプランクなどの腹部を鍛える筋力トレーニングも有効です。
このあと効果的なトレーニングをご紹介します。
ストレス管理
ストレスは脂肪の蓄積を促進する要因となります。リラックスする時間を持ち、ストレスを軽減する方法を探しましょう。例えば、ヨガや瞑想などのリラクゼーション法を試してみると良いでしょう。
睡眠の充実
十分な睡眠を取ることも重要です。睡眠不足はホルモンバランスを乱し、脂肪蓄積を促進する可能性があります。良質な睡眠を確保するために、規則正しい睡眠習慣を作り、快適な寝環境を整えましょう。
これらの方法を組み合わせて取り組むことで、浮き輪肉を効果的に減らすことができます。
浮き輪肉対策における継続の大切さと注意点
浮き輪肉の対策において、継続の大切さと注意点があります。以下にそれぞれのポイントについて説明します。
1. 継続:
浮き輪肉を減らすためには、継続的な取り組みが必要です。一時的な努力だけではなく、長期的な目標を持ち、習慣化することが重要です。定期的な運動や食事の見直しを日常生活の一部として取り入れ、持続的な努力を行いましょう。
2. 注意点:
浮き輪肉の対策を行う上で、以下の注意点にも留意する必要があります。
- 健康的な方法を選ぶ: 急激な減量や極端な食事制限は身体に負担をかけることがあります。健康的な範囲での体重管理を心掛けましょう。
- バランスの取れた食事: 単一の栄養素だけを偏った食事にするのではなく、バランスの取れた食事を摂ることが大切です。野菜、果物、タンパク質、繊維などを適切な割合で摂取しましょう。
- 適度な運動: 浮き輪肉を減らすためには適度な運動が必要ですが、無理な運動やケガのリスクを避けるために適切な方法やフォームを守りましょう。トレーニングの前にウォーミングアップを行い、身体の状態に合わせた運動プログラムを選ぶことも重要です。
- 忍耐力: 浮き輪肉の改善は時間と努力がかかることがあります。忍耐力を持ち、焦らずに取り組むことが大切です。継続的な取り組みが成果をもたらすことを念頭に置いて、努力を続けましょう。
以上の注意点に留意しながら、継続的な取り組みを行うことで浮き輪肉の対策に効果的に取り組むことができます。
浮き輪肉を撃退!おすすめのエクササイズ

最後に浮き輪肉を撃退するおすすめの筋トレ/エクササイズを紹介します。
今回、紹介する筋トレ/エクササイズは、下記の3つです。
- バランスボールエクササイズ
- サイドプランク
- フリパラツイスト
それぞれのやり方を紹介するので、ぜひ試してください。
バランスボールエクササイズ
バランスボールエクササイズとは、その名のとおりバランスボールを使った運動のこと。バランスボールにはサイズがあるため、自分の体型に合ったものを使用しましょう。
一般的には、身長165cm以上が直径65cmで、身長165cm以下は直径55cmがおすすめ。それでは、浮き輪肉の改善に効果的なやり方を紹介します。
- バランスボールの上に仰向けになる
- 肩幅より少し広く開き、膝の真下になるように床にかかとを置く
- 手を開き、両手を伸ばす
- 息を吸いながら、両手を床の方向に伸ばす
- 今度は息を吐きながら、両手を伸ばした状態でおへそを起点とて上体を起こす
- 4と5の動作を約10~20回行う
このときの呼吸は、腹式呼吸を意識してください。
サイドプランク
サイドプランクをすると、脇腹・横腹の腹斜筋を集中的に鍛えることができ、さらに体幹も鍛えることが可能。特に外腹斜筋が鍛えられるため、浮き輪肉となっているお腹周りを引き締めることができます。
浮き輪肉の改善に効果的なサイドプランクのやり方は、下記のとおりです。
- 床に横向きで寝る
- 床側の腕の肘で体の上半身を持ち上げる
- 今度は伸ばした床が側の足の側面で、足の側面で下半身を持ち上げる
- 頭から足までが一直線になったらその状態を30秒~1分間キープする
- 2~4を10回程度行う
- 反対側で同様の動作を行い計3セット行ったら終了
床側の腕の肘で体の上半身を持ち上げる際、床についた肘が肩の真下になるよう心掛けましょう。
フリパラツイスト
フリパラツイストは、たった30秒でできる運動。時間は短いですが、腹筋100回分に相当する運動量といわれています。
浮き輪肉の改善に効果的なフリパラツイストのやり方は、下記のとおりです。
- 床にまっすぐに立つ
- つま先を90度に開いて、両方の踵をしっかりくっつける
- 足の付け根を前に出す
- 両腕を横に水平に上げる
- 両手の親指と人差し指は伸ばし残りの3本は握る
- 腰を左右にフリフリ振る
両手の親指と人差し指を伸ばすときは、「L字」を意識しましょう。
また最後、腰を左右にフリフリ振る際は、頭と足が動かないように腕の水平を保つようにしてください。
まとめ
今回は、浮き輪肉の特徴や原因、改善するために役立つおすすめのエクササイズなどについて解説してきました。
他にも、下記のような有酸素運動も併用しながら行うことで、浮き輪肉を落とすのに有効です。
- ランニング
- サイクリング
- 水泳
- 縄跳び(エアでもOK)
- スクワット
効果的な運動をしても、浮き輪肉となった原因が改善されていなければ、結果として何も変わらないということに繋がりかねません。
浮き輪肉の改善に効果的な運動や食事の見直し、姿勢の改善などを行って、ぜひ浮き輪肉に関連する悩みを解消してください。
(TOP写真提供 = Ryan Moreno/ Unsplash.com)
《参考記事一覧》
浮き輪肉がごっそり落ちる!? 腰回り「激やせストレッチ」(Yahoo!ニュース)
おなかの『浮き輪肉』を落とす!3分でできるマッサージでおなかスッキリ(glico)
腰肉が落ちないのは「癒着」が原因?【加齢とともに増える「浮き輪肉」をごっそり落とす方法】(yoga)
女性専用AIフィットネスでお試し体験募集中!

AIを使ってあなただけの専用トレーニングプログラムをご提案!初心者でも効果的に続けられる女性専用フィットネス。お申込みコードを記載して無料体験!
お申込みコード:HT001