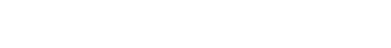サッカーというと、人気スポーツの1つですが、その競技人口はどれくらいなのでしょうか?
日本と世界各国の競技人口について調べてみました。
また、サッカーの競技人口の多さとサッカーの世界ランキングには関係があるのでしょうか?
データを基に、サッカーの競技事情について考えてみます。
日本のサッカー競技人口はどれくらい?
日本のサッカー競技人口については、選手登録数とサッカー推計人口数を、JFAと日本生産性本部が発表しています。
それによると、選手登録数はここ10年間で約90万人。小中高校の部活動、大学のサークルや地域のサッカーチームなどを含めた、年1回以上プレーしている実施率を人口に乗じた数字であるサッカーの競技人口は、2012年には600万人に迫る数字を記録したものの、10年平均では約450万人です。
ちなみに、日本の競技スポーツ種目の中で、サッカーの競技人口は7番目。1位から、ボウリング、水泳、ゴルフ、野球、卓球、バドミントンとなっています。8位以下にはテニス、バレーボール、バスケットボールが続きます。
日本のサッカー競技人口の推移
| 調査年度 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2019 |
| 選手登録数(万人) | 90 | 95 | 96 | 93 | 88 | 88 |
| 増減 | – | +5 | +1 | -3 | -5 | - |
| サッカー推計人口(万人) | 478 | 582 | 415 | 353 | 436 | - |
| 増減 | – | +104 | -167 | -62 | +83 | - |
| 年1回以上実施率(%) | 4.6 | 5.6 | 4.0 | 3.4 | 4.2 | - |
| 増減 | – | +1.0 | -1.6 | -0.6 | +0.8 | - |
※推計人口は、実施率を住民基本台帳の成人人口に乗じて算出(笹川スポーツ財団)。
※選手登録数は、JFAの選手登録者数(JFA.jp データベースから)。
国別サッカーの競技人口ランキング
世界での競技人口は約2億5,000万人と言われているサッカー。世界での競技人口が約4億5,000万人というバスケットボールには及びませんが、それでもサッカーは世界で2番目に競技人口が多いスポーツです。
下記表は、国別サッカーの競技人口ランキングと、WHOが発表した2020年版の世界保健統計の国別の総人口を比べて、割合を出したものです。
国別サッカーの競技人口ランキングと総人口に占める競技人口の割合
| 競技人口順位 | 国名 | 競技人口(×1000人) | 総人口順位 | 総人口(×1000人) | 総人口に占める競技人口の割合(%) | 各国のサッカーの特徴 |
| 1 | 中国 | 推定26,166 | 1 | 1,435,651 | 1.82 | 潤沢な資金でスター選手や有名監督を招へい |
| 2 | アメリカ | 推定24,472 | 3 | 327,096 | 6.85 | 他スポーツでのノウハウを駆使し盛り上げ |
| 3 | インド | 推定20,587 | 2 | 1,352,642 | 1.52 | サッカー熱は高まりつつありこれから |
| 4 | ドイツ | 推定16,308 | 17 | 83,124 | 19.6 | 世界最高峰のリーグ・ブンデスリーガを持ち、観客数もトップクラス |
| 5 | ブラジル | 推定13,197 | 6 | 209,469 | 6.30 | ヨーロッパに選手輩出、サッカー熱高い国 |
| 6 | メキシコ | 推定8,480 | 11 | 126,191 | 6.71 | サッカースポンサー多く、観客数世界4位 |
| 7 | インドネシア | 推定7,094 | 4 | 267,671 | 2.65 | サッカー熱は高いが世界レベルの選手は少ない |
| 8 | ナイジェリア | 推定6,654 | 7 | 195,875 | 3.39 | 身体能力が高く、世界レベルの選手を輩出 |
| 9 | バングラデシュ | 推定6,280 | 8 | 161,377 | 3.89 | これからトップを目指す |
| 10 | ロシア | 推定5,803 | 9 | 145,734 | 3.98 | リーグは極寒で秋冬制、リーグレベルは落ちる |
この表から、競技人口の割合が5%以上の国々は、サッカー強豪国として知られている国々となっていることが分かります。
また、総人口とサッカーの競技人口は比例する傾向にありますが、人口が多ければ必ずしも総人口に占める競技人口の割合が高くなるわけでもないようです。例えば、ドイツは総人口の順位は17位ですが、総人口に占める競技人口の割合は約20%と高めです。これはブラジル、メキシコなどの他のサッカー強豪国と比較しても、かなり高い割合といえますね。
逆に総人口が多いことで中国やインドは競技人口順位ではランクは上位ですが、総人口に占める競技人口の割合で見た場合、競技人口11位のイタリアや12位の日本よりも低い割合となっています(イタリアは8.21%、日本は3.77%)。
また、中国は競技人口が多くても、FIFAランクは高くありません。同じくアメリカは競技人口が多く、割合も高いにも関わらず FIFAランクは伸び悩んでいます。その理由として、中国では「サッカーでは食べていけない」と考えている人が多く、青少年たちがサッカーに打ち込める環境が整っていないことが背景にあるようです。
ドイツでのサッカー事情
前掲の表に見られるように、ドイツでは、総人口約80百万人のうち約16百万人がサッカーをプレーしており、国民の5人に1人がサッカーをしています。
学校での体育の授業はなく、スポーツは地元のスポーツクラブで行われるなど、行政がハードを提供し、民間が運営する仕組みが根付いているドイツでは、スポーツクラブは老若男女が集う場所です。そのため、トップを目指す者も、純粋にプレーを楽しむ者も、年齢に切れ目なく長くスポーツが楽しむことができます。年齢によって分かれているサッカーチームがあるなど、スポーツを楽しむ中から切磋琢磨してトッププレーヤーが出てくる環境は理想的です。
ただ、多くの先進国で問題となっている少子化はドイツでも深刻化しており、ジュニアのうちからサッカーを継続的に楽しんでもらう環境作りが求められています。
FIFAランキングと競技人口の関係は?

FIFAランキングと競技人口の関係について、2018年6月と2020年7月のFIFAランキングと競技人口をまとめました。
2020年7月のランキングでは、ロシアワールドカップ(2018)で優勝したフランス、準優勝のクロアチア、3位のベルギー、4位のイングランドがその後もランキングの上位にとどまる一方、2018年の6月には1位であったドイツが15位に低迷しています。
また、競技人口が少ないベルギーやウルグアイなどの国が、2020年7月のランキングでは上位に入ってきています。このことからも、先述した通り、競技人口が多いということがそのままサッカー強豪国となるわけではないということがわかります。
競技人口では日本よりも少ないベルギー、フランス、ウルグアイ、ポルトガル、スペイン、アルゼンチン、コロンビア。しかし、総人口に占める競技人口の割合はいずれも5%超えです。
| FIFAランキング | 2018年6月 | 競技人口(百万人) | 総人口に占める割合(%) | 2020年7月 | 競技人口(百万人) | 総人口に占める割合(%) |
| 1 | ドイツ | 16.3 | 20.21 | ベルギー | 0.8 | 7.07 |
| 2 | ブラジル | 13.1 | 6.35 | フランス | 4.1 | 6.43 |
| 3 | ベルギー | 0.8 | 7.23 | ブラジル | 13.1 | 6.25 |
| 4 | ポルトガル | 0.5 | 5.29 | イングランド | N.A. | N.A. |
| 5 | アルゼンチン | 2.6 | 6.12 | ウルグアイ | 0.2 | 6.96 |
| 6 | スイス | 0.5 | 6.89 | クロアチア | N.A. | N.A. |
| 7 | フランス | 4.1 | 6.51 | ポルトガル | 0.5 | 5.35 |
| 8 | ポーランド | 2.0 | 5.18 | スペイン | 2.8 | 6.06 |
| 9 | チリ | 2.6 | 14.53 | アルゼンチン | 2.6 | 5.93 |
| 10 | スペイン | 2.8 | 6.14 | コロンビア | 3.0 | 6.04 |
| 参考 | 60 日本 | 4.8 | 3.80 | 15 ドイツ | 16.3 | 19.52 |
| 17 チリ | 2.6 | 13.76 | ||||
| 28 日本 | 4.8 | 3.78 |
※競技人口はFIFAウエブサイトから。総人口は国連人口部の推計人口統計による。
日本のサッカーを含むスポーツ政策と将来性に向けて
日本でも、民間が中学校の施設などを使って運営する、総合型地域スポーツクラブを増やそうという動きがあります。
これまでにも、1995年には8市町村で総合型地域スポーツクラブ育成モデル事業が開始。スポーツ振興法をもとに、2000年にはスポーツ振興基本計画を当時の文部省が定め、総合型地域スポーツクラブを育成。その後、2010年には政府がスポーツ立国戦略を策定し、ライフステージに応じたスポーツ機会の創造を掲げ、2011年には文部科学省がスポーツ基本計画を定めました。
しかし、日本では教育委員会などの団体が学校施設の利用に対し閉鎖的で、外部団体や外部指導者等に施設を貸し出すことに抵抗があります。
また、日本ではスポーツ教育が学校授業の一部となっていますが、これは生徒の人数が多かった時代には底辺拡大に有効であったものの、今や教師が部活動まで顧問として指導するのは限界に来ています。
スポーツ環境をよりよくするためにも、民間が運営する地域密着型のスポーツクラブを増やすなど、地域で活動する機会をより多く作っていくことが重要です。
まとめ
世界では、2番目に競技人口の多いサッカーですが、選手数やチーム数は減少傾向がみられます。しかし、日本でのサッカー人気は維持できているようです。
本記事で紹介したデータを見ると、サッカーの競技人口が多い国よりも総人口に対するプレーヤー人口比が高いほどサッカーの強豪国といえます。
そして、総人口に占めるサッカー競技人口の割合が6%を超えてくると、サッカーがその国でとても身近なスポーツとなり、サッカーの強豪国となる傾向がみられます。
強豪国になるには、トップのナショナルクラスのレベルを上げるのと並行して、サッカーの良さを広めることが重要。そのためには、切れ目なくジュニアからシニアまで身近にサッカーを楽しめる環境を作ることが大切であり、スポーツ環境の整備には官民一体となった一層の検討が急務といえます。
(TOP 写真提供 = matimix / Shutterstock.com)
《参考記事一覧》
世界の人気スポーツ競技人口ランキング2020!年収や稼げる金額についても(体感エンタ)
【国別ランキング】世界のサッカーの競技人口は?FIFAランキングとの関係も徹底解説!(SPOSHIRU)
世界人口ランキング・国別順位(2020年版)(MEMORVA)