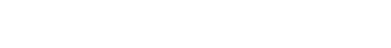パラリンピックは、世界で最も大きなスポーツ大会の一つです。
厳しいトレーニングを積んだトップアスリートたちのパフォーマンスには目が離せません。本記事では、そんな魅力溢れるパラリンピックの起源や歴史について解説します。
パラリンピックとは
パラリンピック(PARALYMPIC)とは、ギリシャ語で沿う、平行という意味のある「PARA」と「OLYMPIC」を組み合わせた言葉。
「もう1つのオリンピック」と解釈されていますが、最初からこのように解釈されていたわけではありません。
パラリンピックが始まった当初は、対麻痺者(脊髄損傷などによる下半身麻痺者)の「PARAPLEGIA」と「OLYMPIC」を組み合わせた「PARALYMPIC」という愛称で呼ばれていました。その「PARALYMPIC」という愛称をつけた大会といえば、1964年に東京で行われた第2回大会が挙げられますが、第2回大会当時、出場者は脊髄損傷などによる下半身麻痺者であったため、「PARAPLEGIAの(対麻痺者)のオリンピック」という愛称を日本が名付けたといわれています。
その後、さまざまな障害を持つ人たちが出場できるようになったことから、現在の解釈へと変化したとされています。
現在の出場対象者は、
- 身体障がい(肢体不自由:上肢・下肢および欠損、麻痺)
- 脳性麻痺
- 視覚障害
- 知的障害
など。
これらの障害を抱えているアスリートで、国際パラリンピック委員会(IPC)の定める厳しい選考基準をクリアした選手がパラリンピックに出場しています。
パラリンピックの起源
紀元前の記録にも障害を抱えた人々がスポーツを楽しんでいたというものがありますが、障害のある人々がスポーツに打ち込めるような環境が整ったのはごく最近のこと。
そして、パラリンピックの起源とされるのは、1948年にストーク・マンデビル病院の病院内で開催された、アーチェリーの競技大会です。
この大会は、医師ルードウィッヒ・グッドマン博士の提唱によって、第2次世界大戦で主に脊髄を損傷した兵士たちのリハビリの一環として行われたもの。
この大会開催日がオリンピックのロンドン大会の開会式と同じ日だったからということから、この大会がパラリンピックの起源であるとされています。
パラリンピックの歴史

1984年に開催された大会がパラリンピックの起源とされていますが、ここからはパラリンピックの歴史について紹介しています。
1960年、第1回パラリンピック、国際ストーク・マンデビル大会開催
第1回パラリンピックは、1960年の9月18日から9月25日にイタリアのラツィオ州ローマで開催された大会です。
この大会には
- アメリカ
- イギリス
- フランス
- オーストラリア
- ローデシア共和国
- ベルギー
- アイルランド
- 西ドイツ
- イタリア
- オーストリア
- オランダ
- マルタ
- スイス
- ノルウェー
- イスラエル
- フィンランド
- アルゼンチンなど
が参加し、8競技57種目が実施されました。
ちなみに、日本は本大会には不参加だったようです。
1964年、愛称が誕生した東京大会
1964年には、第2回パラリンピックが東京で開催されました。
東京大会で実施された内容は、9競技144種目の競技種目。参加国・地域数は22か国で、参加人数は375人に上ったとされています。
東京大会は、全身体障害者の大会にするために、2部制で行われました。
- 第1部:国際ストーク・マンデビル競技大会
- 第2部:全身体障害者を対象にした日本人選手と特別参加の西ドイツ選手数名だけの国内大会
現在、国際的に第2回大会と呼ばれているのは第1部のこと。
日本では、この大会参加をきっかけに障害者スポーツが広く認知されるようになりました。
1988年、「パラリンピック」へ
大会の名称が「パラリンピック」となったのが、1988年10月15日から10月24日にソウルで行われた第8回大会です。
第2回大会以降、パラリンピックはオリンピックとは別都市で開催されていましたが、この大会から、夏季大会が同都市で開催されるようになりました。
ソウル大会で実施された競技種目数は17競技732種目。参加国・地域数は61カ国、参加人数は3,057人に上りました。
ソウル大会の翌年には国際パラリンピック委員会(IPC)が設立され、1988年以降、継続した大会運営が行われるようになりました。
ちなみに、この大会からパラリンピックのシンボルも誕生します。
最初のシンボルとして採用されたのは、オリンピックカラーである青・黄・黒・緑・赤の五色の太極。これが、リレハンメル大会から赤・青・緑の3色に変更されました。
この赤・青・緑の3色は、人間の最も大切な3つの構成要素である、
- 心(スピリット)
- 肉体(ボディ)
- 魂(マインド)
を表現した色といわれています。
その後、アテネ大会の閉会式では赤・青・緑の3色でデザインされた「スリー・アギトス」という選手達の動きを象徴した線に変更されました。
IPC創立30周年に際し、新たなデザインが発表されていますが、これは2024年パリ大会以降で使われる予定です。
歴史に残るパラリンピック開会式
オリンピックというと、盛大で華やかな開会式・閉会式を思い浮かべる方もいるかと思いますが、パラリンピックの開会式もオリンピック同様、盛大で華やかに行われるもの。
歴代のパラリンピック開会式でも特に印象的だったシーンとして2008年北京パラリンピック開会式がありますが、北京パラリンピックの開会式では、聖火ランナー最終走者だった中国のパラ陸上ホウ・ビン選手が車椅子に乗りながら、腕力だけで、地上60mの高さにある聖火台に点火しました。
車椅子とトーチの重さは、合計約16kg。
凄まじいパワーで観客を魅了したのです。
2021年東京大会は、パラスポーツのコロナ禍のモデルとなる大会
2020年8月25日から9月6日までの13日間で開催される予定であった東京パラリンピック。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的流行により1年延期となり、この大会は、史上初めて延期された大会、かつ、同一都市で2回のパラリンピックを開催するという歴史的なものとなりました。
2021年東京大会は、8月24日から9月5日の期間で開催が予定されており、22競技537種目の競技が実施されます。
東京パラリンピックでは麻痺7人制サッカーとセーリングが除外され、バドミントンとテコンドーが新競技として採用されました。
この大会では、スポーツにITを活用。
テクノロジーによるスポーツの進化が体感できる大会として注目されていましたが、コロナ禍でいかにスポーツテックを活用し、どう開催するのかにも注目が集まっています。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大により、さまざまなスポーツ大会やイベントも軒並み中止、延期となるなか、東京大会はコロナ禍でのモデルとなるでしょう。
まとめ
パラリンピックの起源やこれまでの歴史について解説しましたがいかがでしたでしょうか。
オリンピックと同じく、スポーツの発展に欠かせない存在であるパラリンピック。
コロナ禍で無事に東京大会が開催されれば、パラリンピック歴史上初のモデルとして語り継がれることでしょう。
(TOP写真提供 = akihirohatako / Shutterstock.com)
《参考記事一覧》
パラリンピックはいつから始まった?大会の歴史紹介(SPAIA)
欧米スポーツビジネス・最新トレンドの資料を
今すぐダウンロード
HALFTIMEでは、スポーツビジネスのトレンドを「5つのキーワード」から資料で解説しています。以下フォームから無料でアクセスいただけますので、ぜひこの機会にご覧ください。
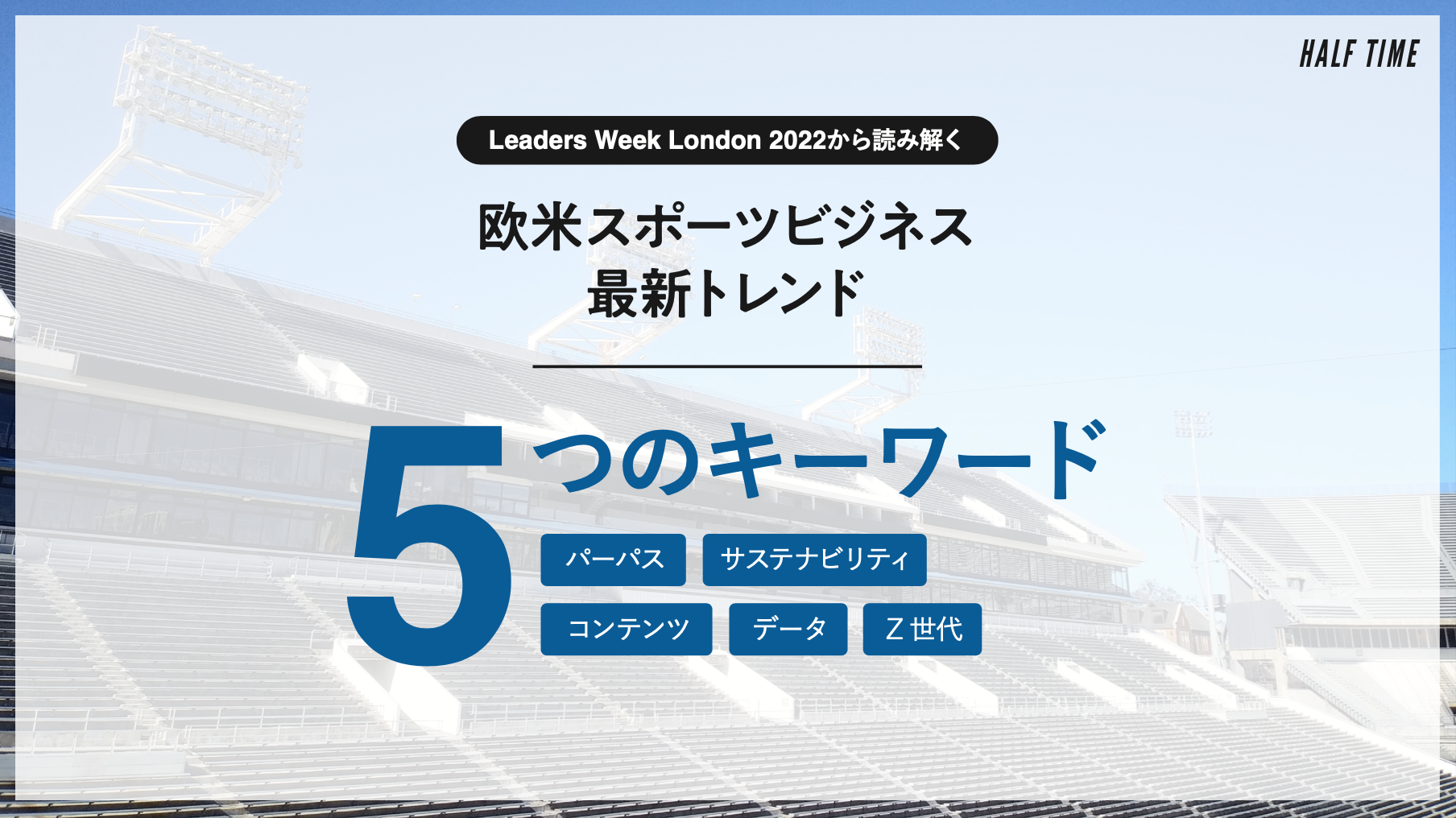
◇資料のDLはこちらから